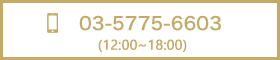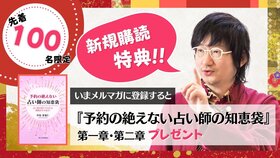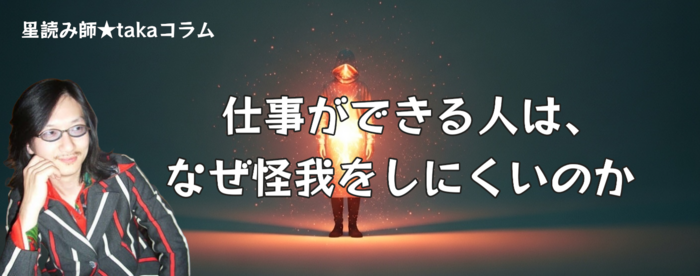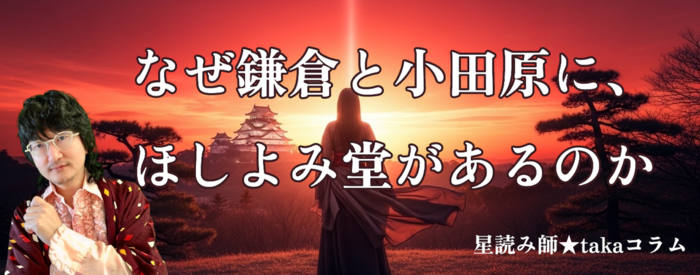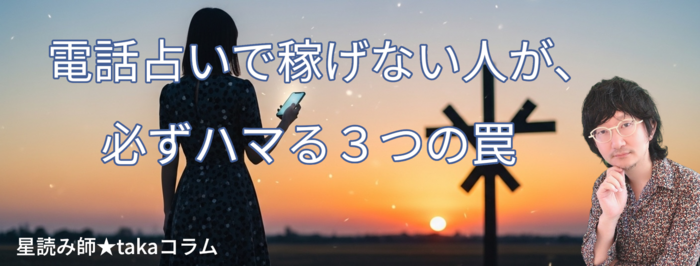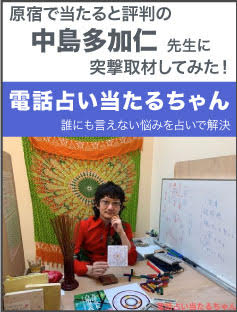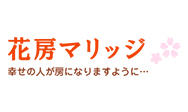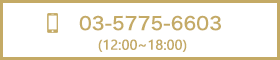年中無休で働くから毎日が休日になる
最近、立て続けに本質的な問いをいただきました。
「病気や障害は強みになりますか?」
「休みたいときは休んでいいのでしょうか?」
この二つ、実は同根です。
どう生きるか。
どう続けるか。
そこに尽きます。
年中無休の真意
ぼくは30年前から、年中無休で生きています。
しかし誤解しないでください。
睡眠は必ず7時間取りますし、体調が悪いときは一切動きません。
これは矛盾ではありません。
これこそが設計なのです。
占い師は、休みたいときに休む。
しかし年中無休である。
この一文の真意を、軽く受け取ってはいけない。
- 身体は休む。
- 志は休まない。
- 労働は止めてもよい。
- しかし研鑽は止めない。
- 観察眼を鈍らせない。
- 思索を中断しない。
- 言葉の純度を落とさない。
これが年中無休。
常時労働ではなく、々これ鍛錬です。
弱さは資源になるか
病気も、障害も、苦労も、整えれば武器になる。
整えなければ、傷のまま腐食する。
ここに分水嶺がある。
弱さそのものが価値なのではない。
弱さを構造化できたとき、それは初めて資源に転化する。
感情の吐露では足りない。
再現可能な言語へと昇華させよ。
痛みを思想へ。
経験を理論へ。
ここまで昇華できた人だけが、他者を導けるのです。
曜日ではなく、状態で生きる
そもそも、土日が休み、週末はオフ。
これは西洋近代の制度設計です。
工場労働を前提とした時間管理の思想。
もともと日本には「週」という概念はなかった。
あったのは、
- 節気。
- 旬。
- 月の満ち欠け。
- 歳時の循環。
- 農は天候で動く。
- 漁は潮汐で動く。
- 山は季節で動く。
「曜日ではなく、状態で生きる」
これが本来の感覚です。
波に従うという設計
占い師も同じ。
土日だから休むのではない。
体調が悪ければ、徹底的に休む。
一日でもよい。
一週間でもよい。
長期休養も辞さない。
逆に、健康で充実しているときは、遠慮なく働けばよい。
波に従え。
固定観念に縛られるな。
固定は消耗を生む。
循環は持続を生む。
常在戦場、しかし常時消耗ではない
ぼくは20年、年中無休。
しかし睡眠は削らない。
体調が悪いときは何もしない。
常時稼働するからこそ、日常は休暇と同質化するのです。
朝は早く起き、原稿をたくさん書く。
夕刻になると酒を飲みはじめる。
その間も会議やラインの返信を欠かさない。
ほぼ毎晩、3〜5時間かけて夕食を楽しむ。
夕食中は、ひとりなら読書か映画鑑賞。
誰かと一緒なら戦略会議。
これは精神論ではなく、持久戦の術です。
無理をして燃え尽きるのは、志が弱いからではない。
設計が粗雑だからです。
曜日で生きるか、循環で生きるか
売れる占い師とは、労働時間が長い人ではない。
続く人です。
そして続く人とは、休むときは完全に休み、
動くときは徹底的に動く人。
曖昧が一番消耗する。
半端な努力は、半端な疲労を生む。
自然に合わせる。
これが純粋日本的精神の一端。
常在戦場であれ。
しかし常時消耗であるな。
削らぬ身体。
止まらぬ志。
あなたは曜日で生きますか。
それとも循環で生きますか。
今日から、設計を整えましょう。
星読み師taka(中島多加仁)